②かんたん看護の歴史:東洋医学の人間像について 人間とは? 人の捉え方
②かんたん看護の歴史:東洋医学の人間像について 人間とは? 人の捉え方
臓器別に細分化することで発展してきた、
西洋医学の立場からみるとお互いに関連性のない症状でも、
東洋医学の側面みると、統一的に把握されることが少なくありません。
そしてこのような考え方は看護に上手く取り入れることによってケアの範囲を拡大させ、
より質の高い看護ケアの提供につながります。 日本の医療、看護教育が西洋医学の影響を受け、
機械論的医療モデルを基礎としていることは 「かんたん西洋医学の歴史」で書きます。
でも、看護の場面においては身体ケアと相まって、より深い精神的ケアの密度が求められることは頻繁にあります。
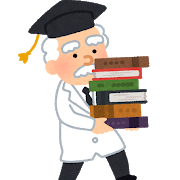
ここでは西洋医学ではとらえきれない東洋医学の人間の捉え方について簡単に書いてみます。
東洋では人の命のつながりについて、 インドに始まった「梵我一一如」という神と人間の一元的ないのち観が重視され、 そのあとのアジアの文化や思想に影響を与えてきました。 そして、それは「心身一如」の人間観を育みました
↑これは難しく聞こえますが、漢字のとおり、心と体は切り離して考えない人間の捉え方です。
ちょっと怪しく聞こえますが、 身体論も含めた宇宙的生命即人間的宇宙という思想である、と言われます。
東洋医学で特徴的な概念は「気・血・水」の要素の存在を仮定しています。
ここではポイントをしぼり、看護をする上で重要な「気」の概念について書きます。
「気」は全宇宙を貫いて存在し、人間などの生命体はこの気が凝集したものととらえます。
そしてその気が離散した状態が死である、と捉えます。 人間を小宇宙、自然界を大宇宙ととらえ、
宇宙の間で気を相互にやりとりしながら生命活動を営んでいると考えます。
つまり、生き物は閉鎖系のように見えますが、外部に開放されている部分があります。
下平唯子 看護師のための東洋医学入門 医歯薬出版株式会社 2012.

「気」の意味は生命エネルギー的なものや心、
または精神を表すものとして使われ、
このような身体のとらえ方は看護に重要な要素となりえます。
↑気ってなんかエビデンス出すのは難しいですが、
「なんだか嫌な気がする」と 思うと急変があったり、
看護をするうえでそういうことってよくあります。
科学的なエビデンスに基づく看護実践では、
患者さんの反応を評価しますが、
そこには看護者自身の在り方は、
あまり評価対象になりません。
西洋医学は二元的な人間観が中心ですが、
それだけでは 極めて個別性の高い看護の本質を見失う危険性があります。

西洋医学を習ってきた私たちは、
疾患を治療する看護中心になりがちですが、
人間はバランスが大事ですし、いつも全体的に患者さんを捉える視点が大切になります。
引用・参考文献
下平唯子 看護師のための東洋医学入門 医歯薬出版株式会社 2012. 田村恵子
看護に活かすスピリチュアルケアの手引き 青海社 2013.
ここまで読んで頂きありがとうございました。
お勧め記事↓ 看護の本質とは care とcure の違い

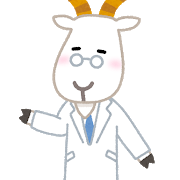
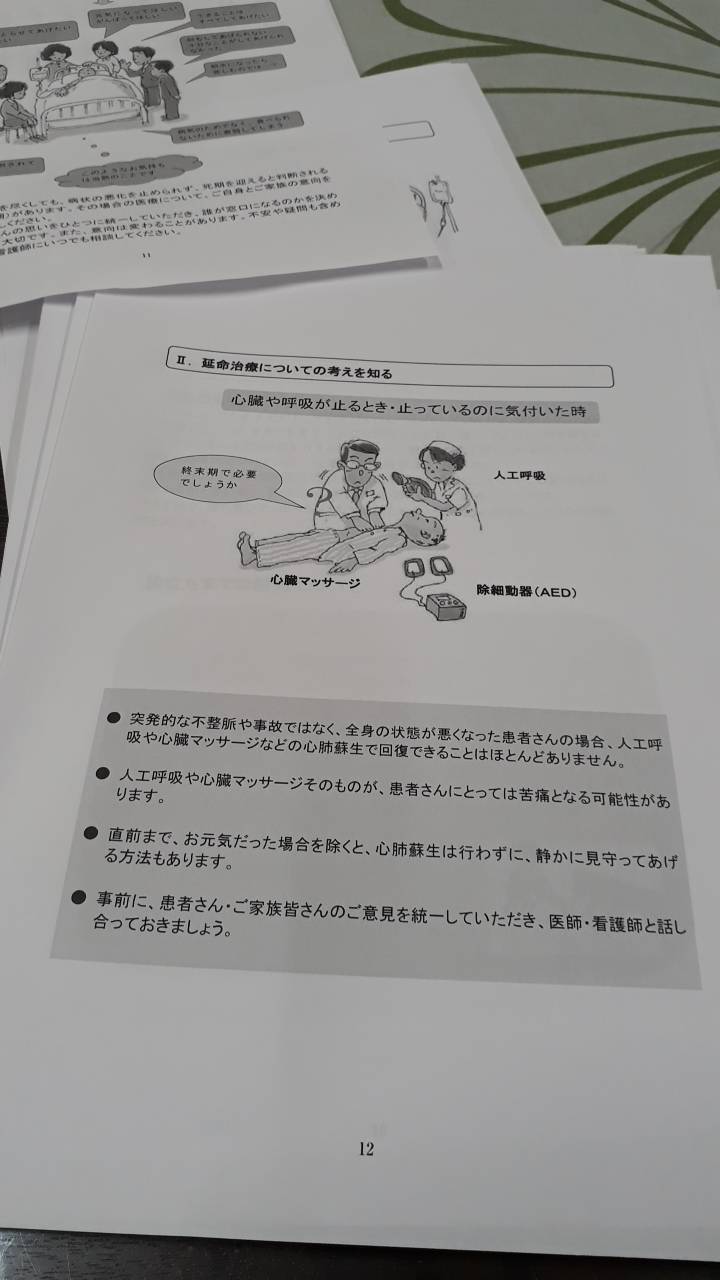
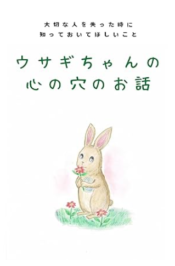
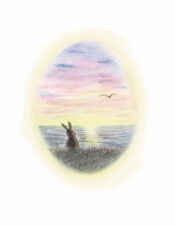
909090.jpg)
