【看護の始まりの話】 そもそも看護の本質とは
前回は健康の定義とスピリチュアルケアについて書きました。
現在の看護の在り方や将来の看護の在り方を考える上で、
看護の歴史を学ぶことは大切なことです。
看護師を長く続けていくと、
時々看護っ何??
と自問自答することがあります。
そういうときは、
そもそもの看護の始まりや歴史をたどってみるのも面白いかもしれません。
歴史や理論は看護実践に含まれている看護の根拠を示していることが多いです。
生物的側面を強調する看護ケア志向により、
あまりスピリチュアリティ(自分の信念や大切なものの意味)
な視点の看護が強調されない時期もありましたが、
スピリチュアリティはずっと看護の一部であり続けたと思います。
そこで、看護における歴史的な流れが3つの形態に捉えて外観してみましょう。
①家族における看護
まず最初は、家族における看護の形態
これは古代から5世紀にかけて、
人間がこの地球に住みついて文明が発達するまでの原始社会、
古代社会において唯一の看護であったのは 日常の家族生活のなかでの家族や、
それ以外の家族あるいは近隣の人々などが行ってきた看護のことです。 引用文献(看護学概論)
看護は家族の中でも特に女性、母親の役割が主要な部分でした。
これは次に述べる宗教的な看護と並行していつの世も行われていました。
人間が共同体をつくり、その中で親が子どもの世話をし、病人が出るとその中の誰かが世話をする。
こうした看護行為は人間の本能的な行為であると言えますね。
②宗教的看護
次に、宗教的看護の形態
これは、6世紀から15世紀にかけて、まだ医学が十分に発達しない時期に、
西欧諸国においてはキリスト教がその時代を支配しており、
このキリスト教の信仰に根差した看護が中心でした。 引用(看護学概論)
つまり、宗教を信じるものの奉仕的看護。
キリスト教信仰に基づき、病人を看護することは、
神への奉仕であり、信仰を確かなものとし、魂の成長を高める行為とされてきました。
看護をスピリチュアルケアの視点で考察すると、
他者を育み、
身体的・精神的及び社会的に良好な状態を図り、
ケアすることが看護の真髄であると考えます。
そしてそれは他者への深い思いやりが不可欠である行為だともいえます。
つまりこのような「他者を助けたい」という動機は自分自身のスピリチュアルな核心から出たものであり、
キリスト教的視点では、他者への愛というスピリチュアルニーズの現れであると言えます。
看護とは自分自身のスピリチュアルな確信から出た行為であり、
宗教的看護の観点から言うと 看護する事は自身のスピリチュアルニーズを満たすための行為であると考えます。
③職業的看護
最後に現在に続く、職業としての看護の形態
前述してきたとおり職業としての看護はなく、
始めはなんら看護の訓練を受けることなく、下層の女性が雑役同様の仕事をしていました。
(←アジアの国だと未だにこういうイメージで看護師を扱ってる人とかいて、悲しい気持ちになる。)
やがてフローレンスナイチンゲールなど看護の先駆者の努力によって
19世紀には看護の訓練を受けた人が看護を職業とするようになります。
そして、近代看護の創設者ナイチンゲールは、
神の教えに適った生き方をしたいとして看護の道を選んだ、
といわれています。
彼女の看護思想の背景には宗教(キリスト教)があったことは周知の事実ですね。
彼女は看護者に求められる思想や態度をキリスト教の教えを基に述べています。
看護を3つの形態に分け、スピリチュアリティの視点から歴史の流れに沿い、
現在にいたるまでを外観してみました。
本来、看護とは人間のスピリチュアリティ(←ここでは信念や、コアとなるもの)
自分の基本的欲求から出た行為なのかもしれません。
つまり看護の本質とは自分の他者の役に立ちたい、
他者をケアしたいという基本的欲求から始まった行為なのかもしれません。
西洋のキリスト教と看護が結びついていたのと同時に、
日本でも仏教と看護はまた密接なかかわりを持っていました。仏教看護の歴史については次回





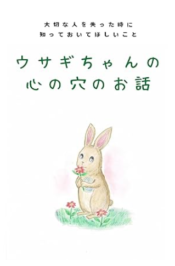
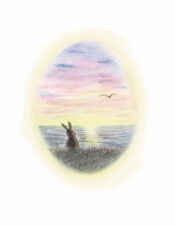
909090.jpg)